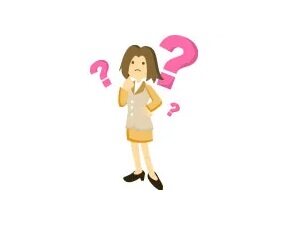ポリカーボネート平板ご購入までの流れ
当店でポリカーボネート板をご購入される前に、ご確認頂きたい事項をまとめました。 必ずご購入前にご確認をお願いします。 ポリカーボネート板とは ポリカーボネートは樹脂製の素材の一つです。透明性があり加工がしやすい材料です。 主な特徴は耐久性です。同じ厚みのアクリル材と比べて約20倍衝撃に強く、弾力性に富んでいます。 また有害な紫外線をほぼカットしてくれるという特徴をもっており、エクステリアではカーポートやテラス屋根の屋根材として使われています。 ポリカーボネート板がカーポート・テラス屋根の張替に向いている理由 屋根の張替の多くは、台風で屋根が飛ぶ、ボールなどが当たって屋根が割れるという理由です。 ポリカーボネートは素材に柔軟性があるため、カーポートやテラス屋根のR曲線に合わせて張替をおこないやすく、また柔らかい素材のため、素材に凹みがあっても割れることは少ないので、アクリル板よりも耐衝撃性があります。 これらの理由で、カーポートやテラス屋根の屋根の張替といえばポリカ―ボネートが非常に多いです。 ポリカーボネート板とアクリル板の違いは? 当店で販売しているポリカーボネート板は、カーポートやテラス屋根が台風などで破損した場合の交換用に販売しております。 カーポートやテラス屋根が販売された当時は、アクリル板が主流となっておりましたが、現在はほとんどの商品でポリカーボネート板が採用されています。 カーポートやテラス屋根材の厚みは約2mm~3mmを前提に設計されており、以前アクリルで取付していたものをポリカーボネートに変更しても問題がない商品がほとんどのため、張替や補修を行う場合、アクリルからポリカに変更される方がほとんどです。 ただし一部のカーポートやテラスは、屋根材が鈍角に曲がっているデザインがあります。(ポリカーボネートは緩やかな曲線、ないしは直線で構成されます。) ポリカは弾力性がある(やわらかい)ため、そういった加工ができません。その場合はアクリル素材とする必要があります。 ご購入までの流れ 1.ご希望のサイズを調べてください。 テラス屋根・カーポートの張替を行う場合、既設の板と同じサイズを正確に測ってください。厚みを測る時は、写真のように、メジャーの途中を基準にして測る方が正確です。この場合たど2mmですね。 縦サイズと横サイズは、正確な寸法が測れない場合には少し大きめのサイズにした方がいいですよ。 サイズが足りないとどうしようもなくなってしまいますが、大きい分には、現地でカットすることで対応が可能です。 ただし、カットしやすいように余裕を持ったサイズにしましょう。例えば10mmをまっすぐに切断するのはとても大変です。 切断は丸鋸を使えば簡単にできます。 ただし、板厚が熱くなると発熱により融着する恐れがあるので、切断速度を落としたり、冷却したりしながら切断するとよいでしょう。 2.サイズの範囲内の商品を選んでください。縦 100~910mm、横 2,001~3,000mm、厚み 2mmの商品番号『20890301』のポリカーボネート平板をお選び頂ければOKです。注意!当店で扱っているポリカーボネート板は、屋根の張替用の商品となりますので、縦は910mmよりも大きいサイズ、横は3,330mmよりも大きいサイズで製作することはできません。また厚みも2mm、3mm以外の取り扱いはございません。ご了承ください。 3.カット無料サービス お買い物かごに入れるを選んで、購入手続きを進めていくと、途中にご要望事項がございます。そちらに『縦●●mm、横●●mm、厚み●●mm』とご記入ください。そのサイズにカットしたポリカーボネート平板をお送りいたします。カット代は無料です。 4.商品の色を選ぶ際の注意点 カーポートやテラス屋根の屋根は、年数が経過すると日焼けして、色が変わってしまいます。 そのため、「台風で屋根が飛んでしまったので、7枚ある屋根のうちの1枚だけ張り替えたい」という場合、絶対に他の屋根と色が変わってしまいます。 また、日に焼けて元々ブラウン系の色だったものが、グレーに近づいたりしていることもあるので、注意してください。 5.屋根の張替えを行う際の注意点 1. ポリカーボネート板には保護シートが貼ってあります。 最初にシートを全部はがしてしまうと、指紋がついたりして汚れやすいですので、シートはなるべく最後にはがすほうがお勧めです。 (作業に支障がでる場合は、先にはがしても問題はないですよ。) また必ず軍手をはめて作業をおこなってください。 2. ポリカーボネート板には裏表があります。 太陽があたる面を表にしてください。逆にしてしまうと、すぐに板が悪くなってしまいます。 これを見れば、ポリカーボネートが丸わかり!おすすめコンテンツ一覧 台風などでカーポートやテラスの屋根が飛んでしまったら?プロに頼むのが一番ですが、実はDIYも可能です。キロは破損した屋根材の計測から購入までをサポートします。 テラス屋根やカーポートに使用されている波板は台風などの強風で飛ばされることや、経年劣化でバキバキに割れているなんてこともあります。見た目が悪いけど、業者に頼めば数万円以上かかるし・・・とほったらかしにしている光景もよく見ますね。 屋根の張替えだけでなく、DIY用部材にもおすすめのポリカ波板の特徴やサイズの見方、おすすめカラーなどの様々な情報をご紹介。
もっと読む